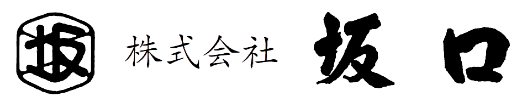営業部
営業マンでありたい。
営業部の朝は、お客さまからの注文メールの確認や、メール・留守電・ファックスなどによる依頼の確認から始まります。 様々な依頼に対し、どのような対応策を立てるか、どのようなプランを提案していくか。一人一人のお客さまの顔を思い浮かべながら、営業マンは真剣に悩み、検討を重ねます。この時こそ彼らが真価を発揮するとき。彼らは、コンサルとしても頼られる営業マン、一声かけると親身になって答えを探し出す営業マンをめざしています。

お客さまに対する手厚いフォロー。これが坂口の強みのひとつです。この強みは1人の営業マンが担当する料飲店の数が少ないことに起因しています。業界では1人300~400軒を担当することが多いのですが、当社ではその半分ほど。それだけ1軒のお客さまに集中することができるのです。
1人が担当するお客さまの数が少なければ社内コストも割高になりますが、「坂口に相談すれば繁盛につながる提案をしてくれる」との評価をいただいてきましたので、これからもこのスタイルを堅持しつつお客さまと共に歩んでまいります。

営業マンの仕事の第一は、担当するお客さまのことをよく知ること。お客さまそれぞれに課題があり、その課題に合わせて提案する内容も変わってくるからです。料飲店を訪れ、お客さまと四方山話をするなかで、いま抱えられているお悩みを聞き出し、ご提案につなげることもたびたびです。
商品に関する新情報をいち早くキャッチし、お伝えする。流行っている店があればリサーチし、それもお伝えする。仕事を離れて飲みに行っても、これはと思うメニューに出会ったら提案につなげる。営業マンはリサーチャーでもあるのです。
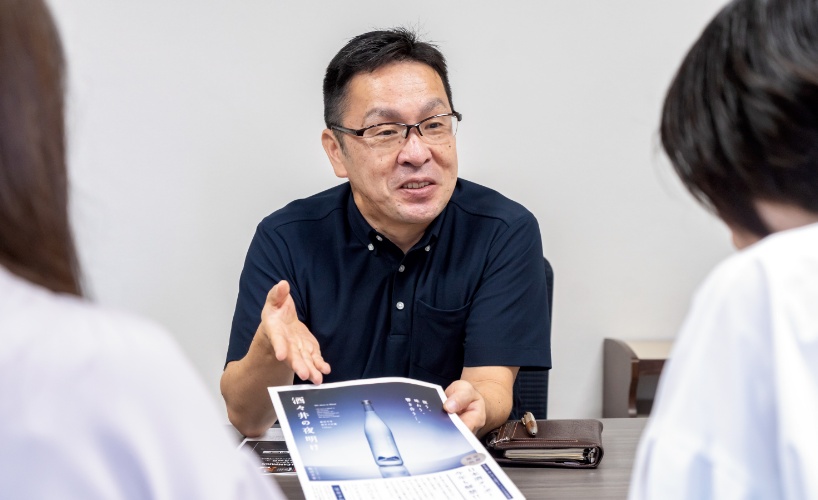
多くの方々にお酒の新境地を堪能していただきたい。この想いから坂口では、「今月のオススメ」と題した自社サイトで限定商品や希少なお酒を紹介しています。また当社では、自社で経営する実験店「スタンドバーSAKAGUCHI」のためのメニューを開発し、好評であればお客さまにご提案することもあります。
このようなことができるのは、社内に「利き酒師」「ソムリエ」「フードビジネスドリンクメニューサポーター」といった認定資格者が複数名在籍しているからです。私たちがお酒もメニューも自信をもってお薦めできるのは、彼らの存在があるからです。

坂口のお客さま—繁盛店ご紹介
ここにご紹介するのは、日頃から坂口とお付き合いいただいている繁盛店。
お付き合いのきっかけ、お店の特徴、こだわり、お薦めの逸品などについて
お話を伺いました。
この地にオープン。 「池林房(ちりんぼう)」
- 浪曼房(ろうまんぼう)
- 犀門(さいもん)
新宿区新宿3-8-8 新宿OTビル9F
代表 太田篤哉(おおたとくや)様

1978年10月にオープンした池林房。お店は新宿三丁目の繁華街にあります。
「オープン前に新宿三丁目の居酒屋でアルバイトをしていたのですが、風情ある新宿三丁目に惹かれて」この地でのオープンになったとのことです。
オープンに際し、太田代表は、当時は珍しかったオープンキッチンスタイルの店舗にこだわりました。
「お客さまと料理人が楽しく語らいながら料理を提供するのが理想でしたね」
客層は、コロナ前はサラリーマンや年配の方が多かったそうですが、コロナ後は、“レトロ感の流行り”からか、若い人たちも増えてきています。
お薦めの逸品は、「季節に合わせたおススメ料理」「定番メニューのジャンボしゅうまい」「こんにゃくとしらす炒め」などなど。これらの料理がお客さまの目の前で次々に仕上がっていきます。
坂口とのお付き合いは1978年から。池林房オープン前、太田代表がアルバイトをしていた居酒屋に、坂口の営業マンが飛び込み営業で訪れたのがきっかけとなりました。
「それ以来、いまなお、営業担当による新商品の提案や、メーカーを介した商品の案内などをしてもらっています。常に話題の商品や人気商品を仕入れることができるので、とても助かっています」
「無形文化遺産—すし」の可能性を追求。 「鮨處八千代飯田橋店」
- 鮨處八千代 別亭
- 立喰い寿司 鮨處八千代新宿三丁目店
- 立喰い寿司 & BAR 鮨處八千代四ツ谷店
- 玄品 銀座一丁目(ふぐ専門店)
新宿区荒木町1番地
代表取締役 中瀬和樹(なかせかずき)様

「鮨處八千代飯田橋店」を1984年にオープンして以来、これまで株式会社八千代は、さまざまなスタイルの「すしの店」を展開してきました。
2004年には「玄品 銀座一丁目(ふぐ専門店)」、2021年には「鮨處八千代 別亭」、2023年には「立喰い寿司 鮨處八千代新宿三丁目店」、2024年には「立喰い寿司 & BAR 鮨處八千代四ツ谷店」をオープン。
その40年余の歩みは、いまや「ユネスコの人類の無形文化遺産」に登録された「和食」の代表とも言える「すし」の可能性を追求してきた歩み。そう断言しても過言ではなさそうです。
「鮨處八千代飯田橋店」が店を構えるのは飯田橋駅の駅前。ロケーションの良さから、地元の方を中心に、家族連れやサラリーマンなどで常に賑わいを見せています。
坂口とのお付き合いは昭和40年(1965年)頃にまで遡ります。きっかけは、株式会社 八千代の前代表取締役・齋藤雅生様と、坂口の前社長・坂口祐吉との出会いだったとか。お二人の間にどのような交流があったのか、興味は尽きません。
日頃、どのようなお付き合いを頂いていますかと中瀬代表取締役にお聞きすると
「酒の仕入全般、頻繁な情報交換、メーカーとの連携などにおいて欠かせない存在。さらには商品開発やラインナップのアドバイスなどももらっています。頼りになるパートナーですね」との答えが返ってきました。
アットホームなお店。 「中島商店」
板橋区坂下1-16-15 都営坂下1丁目第5アパート 15号棟101
店主 中島剛(なかじまつよし)様

中島商店は板橋区坂下の住宅街にあります。板橋区坂下は江戸時代から明治時代にかけては、中山道・街道筋の小集落が点在していたのどかなエリア。その1丁目は、いまは主に住宅地で、学校や公園などが多く見られる、住みやすい場所として知られています。
同店は、まず2003年に板橋区大山にオープン。その後、赤塚(板橋区)・新橋(港区)・志村(板橋区)へ移転。
2020年に板橋区坂下のいまのお店に移転し、現在に至っています。
いまの場所を選ばれたのは、「志村の自宅からほど近いエリアで購入できる物件が欲しくて」とのこと。ようやく格好のお店が見つかったので2020年の新規オープンとなりました。
常連は、ご近所の家族連れやサラリーマンの方々。ここは心からくつろげる店として愛され、皆さん、名物の「手打ち蕎麦」「焼き鳥」「馬刺し」などに舌鼓を打っています。
坂口との出会いは、新橋に店を構えていたとき。営業マンが飛び込み営業で訪れ、温かく迎え入れられたのがきっかけとなりました。
「坂口さんとは、もう長い付き合いになりますね。繁盛店の情報を伝えてもらったり、ちょっとした相談に乗ってもらったり。来訪されると、プライベートなことも含めて四方山話に花が咲きます」と中島店主は笑みを浮かべました。
秋田郷土料理のお店。 「太平山酒蔵 総本店」
(たいへいざんさかぐら そうほんてん)
新宿区四谷1-20 小泉ビル
代表 高橋幸夫(たかはしゆきお)様

現在の太平山酒蔵総本店は、1974年、四谷の飲食店街にオープンしました。
「この地に店を構えたのは、坂口さんからの推奨があったからです」と高橋幸夫代表。
お客さまは会社帰りのサラリーマンや家族連れが多く、皆さん「きりたんぽ鍋」や「比内地鶏料理」など、秋田ならではの食材を使った郷土料理を楽しみに来店されています。
同店と坂口の交流は1966年頃に遡ります。高橋幸夫代表の父君で元会長の高橋和夫様と、坂口の前社長・坂口祐吉の出会いがその始まりでした。
そして高橋和夫様は、坂口が大分むぎ焼酎「いいちこ」の東京地区特約店になるきっかけを作っていただいた恩人でもあります。
いまでこそ「いいちこ」は、“下町のナポレオン”というキャッチフレーズと共に、知らぬ者のないナショナルブランドに成長しましたが、「いいちこ」の製造元である三和酒類が東京進出を計画した当時は、都内の酒類問屋を回っても、どこからも相手にされなかったとか。
そこで三和酒類の創業者・赤松重明氏は、同郷(大分県)の新聞記者に事情を話し、その新聞記者は同じく同郷の高橋和夫会長を紹介し、高橋会長は、取引のある坂口を紹介し、「いいちこの試飲、むぎ焼酎に対する独自の思想、市場戦略や企業姿勢の説明などの有意義な時間を経て(赤松重明氏)」、交渉成立に至りました。
いいちこ成功の陰に、高橋元会長・坂口元社長の協働あり、という訳です。
その後も同店と坂口の交流は続き、高橋幸夫代表は
「新規取扱商品の提案や、業界の情報提供など、今なお多角的に協力してもらっています」と締めくくられました。